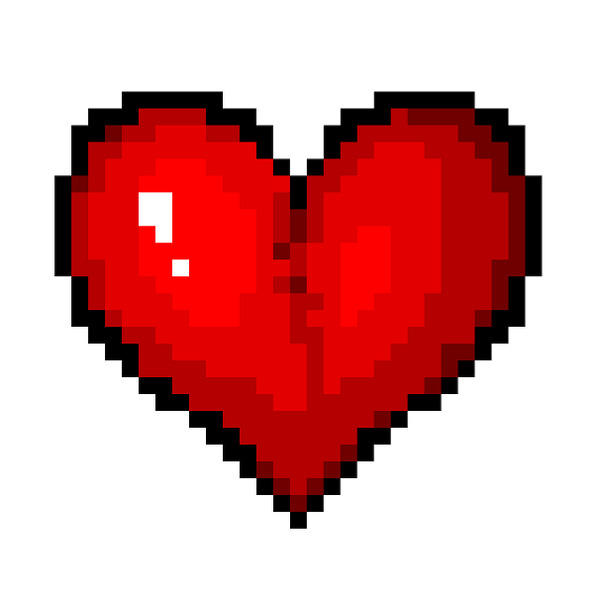この美術という業界にいて不思議だったことの一つは、アカデミー以外に研究をできる公的な場が、明確に用意されていないことだった。
学生たちは美大を出たら放ったらかしで、美大を出ていない者はそもそもこの世界に入ることが出来ない。
それがまずいと思ったので、すこし前から『美研』というのを作った。ここは誰でも参加自由で、美術鑑賞と批評を相互に行い、作品の批評を受けたり、批評に対する批評を受けることができる。
美術は手を動かしてものを作ることだけを指してはいない。それは大変複合的な取り組みであるが、特に(絵画等の平面を含めて)造形芸術の側面について言えば、手を動かし物を作る技術と同じくらい、見る技術が重要である。
人間は肉体的にも精神的にも、摂取したものによって構成される。何かをアウトプットする時、正しく物事を見たり認識した経験による良質なインプットが無ければ、良質なアウトプットはあり得ないのである。
そこで、不足していると考えられる「見る技術を磨く場」として美研を作った。鑑賞批評とは「より鋭く感じ、より細かく分ける行為」である。(さらにその先に「より新しく繋げる行為」としての批評が存在するが、ここでは触れない。)
もう少し詳しく言うと、
知覚(視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚)を通して、より多くの情報を感じ取り、
これらの感じ取ったものを出来る限り細かくより分けて、それぞれの項目に言葉を与えることである。
このように言葉を介さなければ、人間は物事を正しく認識することが出来ない、という考え方がある。無論、その限りではなく、言語を介さずに体感のみで物事を処理できる者もいるが、多くはない。(感覚が鋭敏かつ処理能力が高いアーティストほどこれが出来ているように感じる。)
また、他人の言語を通して新しい知覚の方法に目覚める可能性は誰にでもあるように思う。そういう意味で、他人の作品を他人が批評している様子をよく観察することにさえ、価値がある。それは決して自分に無関係のことではない。
なお、この美研では基本的に「造形芸術の鑑賞批評」に限り行っている。造形芸術ではない、現代美術作品に関しては、別途批評のための場を作る予定である。
なぜなら現代美術と造形芸術は、同じ場で批評を行うには、求められる方法があまりにも違い過ぎるからだ。(そもそもこの二つは歴史的に断絶してはいないが、取り組みとしては本質的に異なる。)
そんなことがあって、美術鑑賞批評研究会を設立した。参加は誰でも歓迎する。共に視野を広げ、各々の制作に活かせることを願っている。
2025/07/15
みつきおぼろ